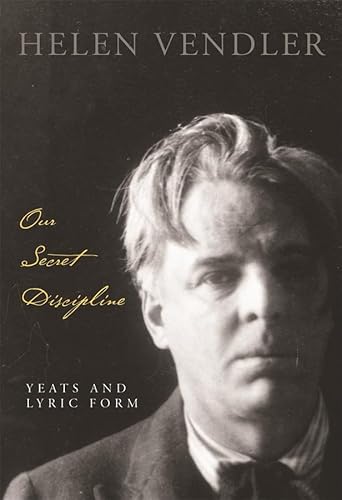一時間ほど研究をした。今日は発表原稿の初稿を一通り音読してみたのだが、30分の時間に収めないといけないのに38分53秒もかかってしまった。学会で発表するというのを数年していなかったらこんなにも分量と読み上げの時間の感覚がわからなくなるのかと驚いた。驚いている場合ではないので、明日はなんとかバッサリと編集して30分に収まるような原稿へと推敲しなければならない。しかし、足りないよりは多いぐらいの方が良いのだ、質疑で補足できるところもあるだろうし、と考えることにしたい。今日は大勢相手の授業もあったので疲れ果てているし、明日またもっとすっきりとした頭で整理しよう。
25/4/2024 (Thu.)
つい一昨日、4月23日にヘレン・ヴェンドラー(Helen Vendler)が亡くなったという。ヴェンドラーはアメリカの批評家で、特に抒情詩について多くの著作がある。
私にとってヴェンドラーは最も尊敬する詩の読者のひとりで、著作を通じて実に多くのことを学ばせてもらった。日本語の翻訳はそれほど多くは出ていないが、それはもしかすると、ヴェンドラーが詩の原文テクストというものに強くこだわり続けた結果かもしれない。彼女は自らを「詳しく論じるテクストがなければどうしようもなく我慢ならない批評家」(“a critic incorrigibly unhappy without a text to dwell on”)と呼んだほど、理論的なことを語るにしても手元に何か文学テクストを置き、それを精読することで議論を進める人だった。*1 だから、その著作を翻訳しようとすれば、必然的に彼女が引用するテクストも翻訳しなければならないし、それには原文が併記されていないと議論が理解できなくなることもある。
ヴェンドラーの仕事は時に批判されることもあった。それはひとつには「精読」という方法を生んだ20世紀の「新批評」や「実践批評」に対する批判とも地続きではあるが(ヴェンドラーはI・A・リチャーズの講義から受けた感銘と影響を隠していない)、ともかく彼女が詩の精読の最も優れた実践者のひとりであったことは間違いないだろう。少しでも日本語でヴェンドラーの業績を知ることができるように、ここに短く、その膨大な全仕事のほんの一部ではあるが、彼女のいくつかの著作を紹介し、私自身の思い出も記録しておこうと思う。
- Poems, Poets, Poetry: An Introduction and Anthology (3rd ed., Bedford/St. Martin’s, 2009)
ヴェンドラーの代表作でありおそらく最も多く読まれたのはこの本だろう。多くの大学の教科書として使われ、改訂版や縮小版も複数出ている。詩の精読の教科書的な本はそれまでにも何種類か出版されていたが、これは類書のなかでも群を抜いて説明が丁寧であり、詩も多く収録されているのでアンソロジーとしての役割も果たしている。ひとりで読むのにも教室で使うのにも向いている。特に、詩を人生の瞬間をとらえたものとして読む第1章 “The Poem as Life” から、そこで扱った詩を再び取り上げ、今度は詩を人生の瞬間をまさにその詩行のかたちに整えて提示されたものとして精読する第2章 “The Poem as Arranged Life” への流れは見事というほかない。惜しむらくは、現在購入するのが難しく、アマゾンなどでも中古の値段が高騰していること。日本語訳が出ることは難しくても(そうなったら画期的なのだが)この本がもっと入手しやすくなれば、英詩に興味がある読者は随分と助かると思う。
私が最初に読んだヴェンドラーの著作もこれだった。学部生のときにアメリカの大学の英文科に留学し、そこで受講したロマン派文学についての授業で、一部が抜粋して配布されたのだった。それは第4章 “Describing Poems” にある、詩を精読するための13の観点だった。たしかその授業の教員は “Vendler’s Checklist” と呼んでいた。これは留学中に詩を読むときの基本姿勢を教えてくれる有益なものだった。そして、ヴェンドラーが亡くなった23日、私はまさかその日に彼女が亡くなることなど知らず、ゼミで学生たちに詩を描写することの重要性を説明していたのだった。ゼミで読んでいたロバート・ヘイデンの “Those Winter Sundays” は、この本でも卓抜な読解が示されている。
- The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics (Harvard University Press, 1988)
ヴェンドラーの批評家としての理論的な立ち位置をよく表したものとしてはこの一冊がある。その副題は前掲した Poems, Poets, Poetry の “Poetry” が “Critics” になった形であり、ここでは彼女が目指す文学批評のあり方が示されている。現在から読むと、当時の批評的潮流のなかで彼女が自らのスタンスを打ち出そうとしていたことがうかがえる。序論の以下のパラグラフにはそれが典型的に言語化されている。
The aim of a properly aesthetic criticism, then, is not primarily to reveal the meaning of an art work or disclose (or argue for or against) the ideological values of an art work. The aim of an aesthetic criticism is to describe the art work in such a way that it cannot be confused with any other art work (not an easy task), and to infer from its elements the aesthetic that might generate this unique configuration. (Ideological criticism is not interested in the uniqueness of the work of art, wishing always to conflate it with other works sharing its values.) Aesthetic criticism begins with the effort to understand the individual work (aided by whatever historical, philosophical, or psychological competence is necessary for that understanding); it is deeply inductive, and goes from the single work to the decade of work, from the decade of work to the lifetime of work, from the lifetime of work to the interrelation with the work of other artists. (p. 2)
真の美的批評の目的は、したがって、芸術作品の「意味」を明らかにしたり、芸術作品のイデオロギー的な「価値」を暴いたり(あるいはそれに大して賛成や反対を述べたり)することを主眼としていない。美的批評の目的は、芸術作品を他の芸術作品とは混同されえないような仕方で「描写する」ことであり(それは簡単な仕事ではない)、その要素から、この作品固有の配置を生み出しているであろう美的な原理を「推論する」ことである。(イデオロギー批評は芸術作品の固有性というものに関心をもたず、常に作品をその作品と価値(観)を共有している別の作品群と混ぜ合わせようとするものである。)美的批評は個々の作品を理解しようとする努力から始まる(その理解に必要であれば、歴史的、哲学的、心理学的なあらゆるものを手助けとしながら)。それはきわめて帰納的な営みであり、一つの作品からその芸術家の10年間の作品へ、その芸術家の10年間の作品からその芸術家の生涯の作品へ、そして、その芸術家の生涯の作品から他の芸術家の作品へと進んでいくのである。
ヴェンドラーは自らの批評を「(審)美的批評」と、つまり、あくまでも文学テクストを芸術作品としてみる姿勢を崩さないものと述べる。彼女の読解の出発点には、芸術としての言語に出会ったときの感性的反応がある。そして、その反応は作品のどのような言語的配置によってもたらされたのだろうかという問いを携えて、彼女は詩を隅々まで観察し、描写する。出版年の順序としては Poems, Poets, Poetry は本書の後に出されたものであり、したがって、本書が理論編であるとすれば前掲書はその実践編として位置づけることもできる。
もちろん本書にもその実践となる詩論、詩人論は豊富に含まれている。ただ、それらは個別のエッセイ(論考)として掲載されているので、少し難しいと感じるようであれば前掲書から読むことをすすめる。あるいは、本書の内容の一部は日本語訳も出版されているから、以下を手に取るのもひとつの手だろう。
The Music of What Happens というタイトルは、ヴェンドラーの友人・同僚でもあったシェイマス・ヒーニーの詩行から採られている。彼女は、美的批評家というものは作品のなかで起こっていることだけに注目してはならない、その起こっていることがどのように起こっているのかに注意しなければならない、と主張する。ヒーニーの言葉を詩に敷衍して言えば、詩とは何か出来事を述べているのではなく、出来事を音楽によって表現しているのであり、批評家はその音楽にこそ耳を澄ませなければならないということになる。
ヴェンドラーとヒーニーという話題では、以下の本にも触れないわけにはいかない。
- Seamus Heaney (Harvard University Press, 1998)
1995年にノーベル文学賞を受賞したヒーニーの作品について、その詩集を時系列で論じた作家論。しばしば精読という営みは作家をいったん排除する(ちょうど「ただし摩擦は考えないものとする」といった風に)ものと考えられがちだが、少なくともヴェンドラーの精読のスタイルはそうではない。彼女はテクストを重視しつつ、その芸術作品を生み出した芸術家に対しても注意を払うのを忘れない。もちろん、大量の詩人の作品を扱っているから、時には専門家から見ると不十分な知識で論じている箇所もないではない(そういう批判も多い)。しかし、少なくともそれは作家への敬意をないがしろにした結果という種類のものではない。あるいは少なくとも、ヒーニーについての詩人論を読んでいて、そういう疑念が湧くことはない。
ヴェンドラーの二冊しかない日本語訳書のうちのもう一冊は、このヒーニー論である。
この訳書のまえがきでは、翻訳に至った経緯と共にヴェンドラーが1989年に来日して講演をしたことなども記録されている(前掲の訳書も学会での特別講演が縁で刊行されたという)。私自身はそのときに生まれてすらいなかったし、結局ヴェンドラーと直接会うこともなかったので、その種の情報の貴重な資料としても読んだ。ただし、この翻訳は読みやすいとは言えないことも正直に書いておきたい。いわゆる直訳調というか、原文で読むときよりもごつごつとした感じがするのは否めない。ただし、それはヴェンドラーの英語にあまりにも英語的な表現が多くて日本語にするのが難しいからというのもあるだろう。
ヴェンドラーによる詩人論的著作には、ヒーニー論以外にも優れたものがいくつもある。例えば、彼女が愛読した二人のモダニズム期の詩人、アイルランドのW・B・イェイツとアメリカのウォレス・スティーヴンズは、彼女の批評家としてのキャリアの初期から最後まで詳細な読解の対象であり続けていた。
- Yeats’s Vision and the Later Plays (Harvard University Press, 1963)
- Our Secret Discipline: Yeats and Lyric Form (Belknap Press, 2007)
- On Extended Wings: Wallace Stevens’ Longer Poems (Harvard University Press, 1969)
- Wallace Stevens: Words Chosen Out of Desire (University of Tennesssee Press, 1984)
イェイツやスティーヴンズの批評史において、ヴェンドラーは欠かすことのできない存在だろう。イェイツについては、彼女が長年教鞭をとったハーバード大学での講義がYouTubeに公開されている。この講義では、 “Among School Children” を題材として、詩に必ずしも関心を持っていない学生に対して彼女がどう教えているのかを見ることができる。
また、彼女とスティーヴンズとの関係は、狭義のアカデミアに限られたものではない。いわゆる批評や研究に興味はなくとも、ヴェンドラー編の以下のスティーヴンズ詩集を持っているという英語圏の詩の読者は多いはずだ。
- Helen Vendler, ed., Stevens: Poems (Everyman’s Library, 1993)
スティーヴンズの有名な詩に “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird” というタイトルのものがあるが、確証はないものの、ヴェンドラーが Poems, Poets, Poetry で13の観点を提示したのも、いわば “Thirteen Ways of Looking at a Poem” とでもいうべきオマージュだったのではないかと思っている。
それから、ジョン・キーツの一連のオードを徹底的に論じた以下の著作も忘れ難い。
- The Odes of John Keats (Belknap Press, 1983)
私自身、卒業論文を書くときに扱う作家の候補のひとりにキーツがいて、その流れで本書を図書館で借りて勉強したことをよく覚えている。ひとつのオードにつきひとつの章があてられていて、こんなに真正面から作品論に取り組んでいいのかという清々しい驚きと、こんなに精緻な読解ができるのかという憧れは、しかしながら、これだけ論じられてしまっては何を言えばいいのかわからないと学部生の私に思わせもした。結果、私はキーツとは別の作家で卒論を書いて、今も研究面ではロマン派からは遠ざかり続けている。もっとも、当時の自分がどれだけ読めていたのかは怪しいし、今読み返すとまた違った感想があるかもしれない。
しかし、ヴェンドラーが作家単体を扱った著作からおすすめを選ぶとすれば、シェイクスピアとディキンソンを取り上げた以下の二冊になるだろう。
- The Art of Shakespeare’s Sonnets (Belknap Press, 1997)
- Dickinson: Selected Poems and Commentaries (Belknap Press, 2010)
前者はシェイクスピアのソネット154篇全てについて詳細な読解を付すという、ヴェンドラー的精読の実践のひとつの到達点ともいえる著作。もちろんシェイクスピアのソネットには、戯曲と同じように、例えばアーデン版テクストのような専門家による注釈が多く付いたものが存在している。しかしヴェンドラーが付記するのは専門的知見を示す注釈ではなくエッセイ形式のコメンタリーであり、時にはソネットの言語的配置を視覚化するための図も示される。詩を図式化してみることの意義を、私はこの本を読んで知った。
シェイクスピア学者による注釈書というわけではないから、特に研究者のなかにはヴェンドラーのあまりにもテクスト中心的な解釈には無理があるだろうと反感を隠さない向きもある。実際、私の尊敬する研究者のなかには、彼女を好まないという人もいるし、その理由もよくわかる。この点については、例えば、ヴェンドラーのシェイクスピア本の書評であり名エッセイでもある圓月勝博「秘教の批評、畢竟、批評の秘境」(『関西英文学研究』2014所収)を読むとその一端がわかるだろう。
ただ、いかに欠点があろうとも、『ソネット集』をはじめから愚直に、それでいてテクストに絡みつくように読み進めていくヴェンドラーの筆致からは学ぶところが多いのは否定できないように思う。
もうひとつの、ディキンソンについての本も、ひとつの詩につきエッセイ形式のコメンタリーが続くという構成になっている。英語的にも内容的にも、シェイクスピアのものよりも初学者や学部生にとってはディキンソンのものから入る方が良いだろう。分量はだいたいひとつの詩に対して2–3ページほどで、長いものでも5ページぐらいなので、英語で書かれた詩の批評文を読んでみたいという学部生にはぴったりの素材になると思われる。
ヴェンドラーのテクストへの絡みつきは、かつて詩を読むことが詩行を覚えて誦じることとほとんど同義だった時代を忘れまいとする彼女の姿勢を反映してもいる。ソネット本の序論で、ヴェンドラーはこう言っている。
To arrive at the understandings proposed in my Commentary, I found it necessary to learn the Sonnets by heart. . . . No pianist or violinist would omit to learn a sonata by heart before interpreting it in public performance, but the equal habit of knowing poetry by heart before interpreting it has been lost. (pp. 11–12)
私のコメンタリーで提唱されている見解に辿り着くのに、私は『ソネット集』を暗記しているのが必要不可欠だと思った。……ピアニストもヴァイオリニストも、人前の演奏でソナタを解釈するのに事前にソナタを暗記することを怠ることはないだろう。しかし、それと同じように詩を解釈する前に詩を暗記するという習慣は失われてしまっている。
果たして、現代の詩の研究者のどれくらいが自分が論じる詩を暗誦できているのだろう。
他方で、覚えるに値する美的に優れた詩を特権視し、「イデオロギー」のみで作品を判断するのを避けようとしたヴェンドラーに対して、特に晩年は批判の声も目立った。2011年に出版された The Penguin Anthology of 20th-Century American Poetry に対してヴェンドラーは「これらは覚えるべき詩なのだろうか?」(“Are These the Poems to Remember?”)というタイトルの書評を書き、次のように述べた。
Multicultural inclusiveness prevails: some 175 poets are represented. No century in the evolution of poetry in English ever had 175 poets worth reading, so why are we being asked to sample so many poets of little or no lasting value? Anthologists may now be extending a too general welcome. Selectivity has been condemned as “elitism,” and a hundred flowers are invited to bloom.
多文化を包摂しようとする態度が支配しているのだ。175人ほどの詩人が選出されている。英語詩の発展において、175人もの読む価値のある詩人をもった世紀など存在してこなかった。ならばどうして私たちは、ほとんど、あるいは全く後世に残る価値を持たないこれほど多くの詩人を標本する必要があるのだろうか? 今の時代、アンソロジー(詞花集)の編者はあまりにも何でも受け入れるようになりすぎているのかもしれない。精選という営みは「エリート主義」として非難され、何百もの花が咲くようにと招かれているのだ。
書評ではその後、より具体的には、「編者はスティーヴンスの詩をたった五篇の初期の作品だけ入れればいいと思ったのだろうか?」などの不満が続く。このアンソロジーの編者であり、1993年から1995年までアメリカの桂冠詩人を務めたリタ・ダヴは、この書評に対して「アンソロジーを弁護する」(“Defending an Anthology”)という返答記事を書いた。ダヴはこう反論する。
Assuredly, many acclaimed poets are no match to Shakespeare—probably not a one, not even Walt Whitman. But The Penguin Anthology of Twentieth-Century American Poetry is not meant to be an in-depth scholarly study of pick-your-ism; it is a gathering of poems its editor finds outstanding for a variety of reasons, and by no means all of them in adherence to my own aesthetic taste buds; my intent was to offer many of the best poems bound into books between 1900 and 2000 and to lend a helping hand to those readers wishing to strike out on their own beyond this selection. Part of the problem with the phenomenon one could call poetry politics is the reluctance of many scholars to allow for choice without the selfish urge to denigrate beyond whatever doesn’t fit their own aesthetics; literary history is rife with stories of critics cracking the whip over the heads of ducking artists, critics who in their hubris believe they should be the only ones permitted to render verdicts in the public courts of literature.
確かに、多くの称賛されている詩人たちもシェイクスピアには匹敵しない——おそらくひとりも、ウォルト・ホイットマンでさえも。しかし、The Penguin Anthology of Twentieth-Century American Poetry は「自分で選ぶ式」の詳細な学術的研究であることを目指したものではない。編者がさまざまな理由によって素晴らしいと思った詩を集めたものであって、それらの全てが私自身の美的趣味に一致する蕾であることは決してない。私の意図は、1900年から2000年の間に書物へとまとめられた詩の多くを提供し、このセレクションに満足することなく自分でも詩を探してみたいと願うような読者たちに助けの手を差し伸べることであった。詩の政治学とでも呼べるような現象の問題のひとつは、多くの学者たちが自分の美的趣味に合わないもの以外はけなしてしまう自己中心的な性質によって選択の余地を許そうとしないことにある。文学史というのは、批評家が鋭い音を立てて芸術家の頭をムチで打とうとして芸術家がそれをかわそうと頭を下げるという物語に満ちている。その傲慢によって自分だけが文学という名の公衆の裁判所で評決を下すことが許されている人物だと信じている批評家たちの物語だ。
ダヴの反駁において、ヴェンドラーが目指す(審)美的批評は問題含みの「詩の政治学」の実践であり、ヴェンドラーが批判したまさにその「イデオロギー」によって詩人や読者を制限する行為とされる。結局、イデオロギーから自由になることはないのだから、それは美的批評が受けざるをえない当然の指摘だろう。
もちろん、この二つの記事だけを読んで、両者のどちらか一方だけを支持するよりも、実際に二人が編んだ詩を読み比べる方が良い。ヴェンドラーもまた、ダヴと同じような編纂の仕事を引き受けてアンソロジーを出版している。そこには、ダヴの詩も含めて、彼女が選んだ20世紀アメリカ詩の数々が収められている。
- The Anthology of American Contemporary Poetry (I.B. Tauris, 2003)
ヴェンドラーが実演してみせた、時に怪しげで、時に偉そうにすら思える詩の読み方は、多大な影響を与えてきたし、これからも与え続けることは間違いない。表面的にはその影響力が見えづらいとしても、批評家や研究者に限らず多くの英詩の読者は彼女の著作を通じて精読を学んでいるし、多くの英詩の授業は彼女の著作に影響を受けた教員によってなされている。授業の元ネタが彼女の精読にあるという人は(私も含めて)少なくないだろう。そして、ヴェンドラーがそう自称したように、論じるテクストが手元になければどうしようもなく我慢ならない詩の読者たちは(私も含めて)、彼女が残してくれた膨大な著作をめくりながら、その読みに頷いたり首を傾げたり、彼女のムチを避けようと頭を下げて反撃したりし続けていくのだろう。
*1:Helen Vendler, The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics (Harvard UP, 1988), p. 9.
24/4/2024 (Wed.)
今日も雨で気分が乗らない一日だった。地元は雨が多いことで有名だったが、こっちに引っ越してきてから天気が悪い日の多さでいうと大して変わらないんじゃないかと思うぐらいだ。早く夏の始まりぐらいの季節になってほしい。
そうは言いながらも研究は進めた。今日は授業がひとつだけだったので、それ以外の時間を見つけてなんとか三時間ほど発表原稿の執筆。昨日で難所をなんとか超えたので、ラストに近いところまで進んだ。おそらく明日で一通り最後まで行くだろうから、そこからもう一度音読してみて時間をはかり、全体を推敲する。
それ以外にも年金関連の手続きをしたり校務で書類を書いたりしていたが、授業準備の一環でアディーチェの「なにかが首のまわりに」を読み返して考える時間をとることもできた。
- チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ(くぼたのぞみ訳)『なにかが首のまわりに』(河出書房新社、2019)
アディーチェの小説は読者にいろいろと語らせたくなる作風で、おそらく学生からも意見が出やすいと思うが、この作品で最も注目すべきことのひとつは、二人称の語りで書かれていることだろう。その点を授業のなかでは考えていきたい。
23/4/2024 (Tue.)
3コマある日で、先ほど最終コマを終えてコンビニで夕飯に弁当を買って食べた。どうしても講義パートの割合が多いと肉体的には疲れてしまう。最終コマは3年ゼミで、詩を描写して精読するというテーマでロバート・ヘイデンの “Those Winter Sundays” を読んだ。この詩は英語圏では有名だが、読むたびにため息がでるほど素晴らしいと思える。ヘイデンの詩集は翻訳されていてもまったくおかしくなさそうなのだけれど。
研究の方では、原稿執筆の続きを少しだけ進めたが、どうにもスタックしていて分量はあまり書けなかった。ただ、一番の難所はなんとか終わりそうなので、明日以降はもう少し良い具合のペースで進むと信じたい。
22/4/2024 (Mon.)
今週中には発表原稿を仕上げたいので、午前中はしっかりと原稿を進めるつもりだったが、朝から雨が降っていたのもあってあまり集中できなかった。それでも、これはまずいなと思ってひとまず現時点までの部分を音読して時間を測った。今のところ18分ちょっとぐらいで、もう少しゆっくり読んでも20分程度になるだろう。発表時間は30分なので、だいたい3分の2ぐらいになっている。アウトラインとしてはちょうどいいぐらいの感じだし、ひとまずこのペースで書き進めて問題ないだろうということはわかった。
午後は今週ぶんの授業準備。今週はわりかし準備が必要なものが二つあるのだが、良い具合にほとんど終わらせることができた。あとは明日少しだけやれば今週は問題なく終わるだろう。それ以外の時間で原稿に集中したい。
21/4/2024 (Sun.)
じっくりとした睡眠を終え、午前中は軽く授業準備をした後、執筆ミーティング。今週はひとつオムニバス授業の担当回があり、大人数相手に講義をするので、そのためのスライドを作成した。ミーティングの方は、いつものように雑談と放言が中心になったが、ここ最近は毎週執筆目標を達成できているのでよしとする。
昼にツナと海苔のパスタをつくって食べた後、陽光が差してきたので気分が良くなってきて外出することにし、数週間ぶりに図書館に行った。今回は自習室での研究ではなく、書架を物色しながら読書のための本探しをした。結果、以下の5冊を借りて読む。バスで帰って家に着く直前には小雨が降り始め、良いタイミングで外出を終えることができた。
19世紀末のデカダン芸術はフランスを中心にヨーロッパで栄えたが、この文脈ではイギリスでも優れた書き手が何人か現れた。ダウスンもそのひとりで、彼の詩はいくつか読んできたが、岩波文庫から訳書が出ているのは知らなかった。書店では見かけたことがないと思う。翻訳はこの手のジャンルで有名な南條竹則によるもの。雅語、文語の訳も詩のトーンに合っている一方で、例えば次の、アーサー・シモンズへと贈られた「憂鬱(スプリーン)」の、素朴な言葉づかいの詩行も名訳だと思った。
悲しくはなかった。泣けもしなかった。
思い出はどれもみな、眠りについていた。
川が次第に白く不思議な様子に変わるのを、
夕暮れまで一日中、僕は見ていた。
夕暮れまで一日中、僕は見ていた。
雨粒が窓硝子を物憂げに打つのを。
悲しくはなかった。ただ、かつて欲しいと思った
すべてのものに飽きがきただけ。
彼女の唇、彼女の眼も、昼の間は
まるで影の影となり果てた。
彼女の心への憧れも、昼の間は
忘却と化していた。それが夕暮れになると、
僕は悲しく、泣きたくなり、
思い出はどれもみな、眠れなかった。(pp. 37–38)
先日投稿した論文で扱ったトピックのひとつの文脈にはジャポニスムがあった。そこでは特に英語の詩を論じていたので、俳句のような文学との関連が第一に問題になるのだが、その詩人は浮世絵にも関心を示していたし、実際にそれを自らの詩のモチーフにも取り込んでいた。そういうわけで、ここしばらくは頭のなかで19世紀末から20世紀初期にかけての西洋における日本的なものについて考える時間が長かった。論文は投稿もし終えたし、ひと段落したのだが、せっかくこうしてジャポニスムの問題系が頭のなかに浮遊しているあいだに、美術でどのような運動があったのか、それがどう論じられてきたのか、を少し知っておこうと本書を手に取ったのだった。
ぱらぱらとめくる感じ、特に第七章「空間のジャポニスム」、第八章「線のジャポニスム」が面白そうだ。特に第七章では「絵画の縁によるモチーフの唐突な切断」(p. 183)が話題になっていて、このあたりは当時の詩とも似たことが指摘できると思う。
同じく美術関連で、つい数ヶ月前に出版されていて読みたいと思っていた本。キリスト教美術についての類書はこれまでもいくつか読んできたが、見たことのない図版も多く、文章パートも語り口調で親しみやすい。大きな特徴は、中世ヨーロッパの作品がメインになっているところだろう。その理由は「はじめに」で次のように説明されている。
なぜ中世か、というと、キリスト教美術の黎明期、草創期であることから、表現がまだ定型化されておらず、聖書解釈にゆれや、まよい——いいかえれば、創造性、独自性がみられるからです。中世のキリスト教美術には、早春のようなあかるさ、のびやかさがあります。(pp. 1–2)
確かに、類書でよく取り上げられるルネサンス美術には、写実的で見事な美しさがある。しかし、そういった完全性の美をもたないからこそ、より自由で生き生きとした表現を中世美術には見て取れる、という、言われてみればそうだという発想で本書は編まれている。見た瞬間に笑ってしまうような、なんとも間の抜けたような絵も多い。適当にページを開いているだけで楽しめるし、解説の文章を読むとさらに面白くなる。
- 中村達『私が諸島である——カリブ海思想入門』(書肆侃侃房、2023)
こちらも数ヶ月前(といっても、もう半年近く前)に出版された一冊。ウェブ連載のときから話題になっていたが、これは本の形式で読みたいと思っていた。著者は西インド諸島大学モナキャンパスの英文学科(The Department of Literatures in English)に日本人として初めて在籍して2020年にPhDを取得している。その経歴がそのまま本書のテーマにつながっている。
その内容がきわめて刺激的であることはすでに多くの評者が称賛しているところだが、同時にその洗練された文章にも注目すべきだろう。専門書あるいは学術書の美点と、一般読者に開かれた教養書としての美点が、読みやすくかつ明晰な文によって併存している。カリブ海の思想や文学に関心を持つ人は確実にこの本によって増えるだろう。今期担当している授業でも学生たちに薦める予定。
- 吉増剛造『静かな場所』(書肆山田、新版、2010)
この数年、著者の本を意識的に多く読んでいたが、これは未読だった。こういう本もしっかり蔵書のなかにあるあたり、近所の図書館に恵まれているなとしみじみ。アメリカでの生活が主に綴られたエッセイ集で、写真もついている。「栗鼠の家」と題されたものには、次のような思い出が記録されている。
歩いて行って樹の下に立ちたい。そんなことを考えていたのは、英語の栗鼠(Squirrel)の発音が、(r)と(l)が入りまじって難しいので、あの動物は私にとっては存在しないも同然だと冗談をいっていると、ある女性が彼らは一匹ずつ樹上に巣をつくり独立して生活しているという、その話におどろいて、栗鼠の家の下に立ちたくなっていた。(pp. 98, 100)
squirrelの発音がこんがらがってしまうのは、自分も小学生のときにそう思ったのをよく覚えている。ところで、このエッセイからずいぶん時間が経ってから書かれた長篇詩「怪物君」は「アリス、アイリス、赤馬、赤城/イシス、イシ、リス、石狩乃香」と始まるが、ここでの「リス」という言葉の陰には、詩人がアメリカで憧れた栗鼠の姿が隠れているのかもしれない、などと夢想した。
20/4/2024 (Sat.)
申請書の昨日できなかった部分を書き終え、全体を何度か見直したうえで提出した。これで今週の目標はすべてクリアしたことになる。今週はわりと帰る時間が遅い日が多かったので、無理せずに研究はこれだけで終えることに。いやはや。